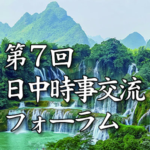新しい農業の仕組みや地域再生をめざす
グリーンコープ生活協同組合ふくおか理事長 坂本 寛子

緑の山に囲まれた青空の下、こうべを垂れ、たわわに実った稲穂が風を受けて揺れている。その一角に、稲の黄金色ではない、深い緑色が目を惹きつける。大人の胸ほどの高さまで成長したサイレージ(飼料)用トウモロコシだ。
ここは、福岡県田川郡赤村にある圃場。赤村ではグリーンコープの産直生産者たちが、有機栽培や化学合成農薬をできるだけ使わない農法で、トマトやセロリなどを中心にさまざまな野菜を、そしてその土地の名前を冠した「赤村のめぐみ」という米などを生産している。グリーンコープの鳥越ネットワークの生産者たちだ。