600年を超える友好交流の歴史を再確認
参議院議員 伊波 洋一

沖縄から戦争に反対し平和を求める声を中国の人々に届けるために「広範な国民連合」の協力を得て2023年12月25日~30日に「沖縄平和友好訪中団」(6人)で中国の首都・北京市を訪問し、関係団体との平和友好交流を行うことができた。お世話になった中国の関係方面の方がたに感謝申し上げます。
参議院議員 伊波 洋一

沖縄から戦争に反対し平和を求める声を中国の人々に届けるために「広範な国民連合」の協力を得て2023年12月25日~30日に「沖縄平和友好訪中団」(6人)で中国の首都・北京市を訪問し、関係団体との平和友好交流を行うことができた。お世話になった中国の関係方面の方がたに感謝申し上げます。
東アジア共同体研究所所長・元外務省情報局長 孫崎 享

(1)「外交問題評議会(CFR)」が考える危機
米国の各種研究機関で最も権威があるCFRは「24年に注目すべき紛争;予防上の優先事項に関する調査結果」を発表した。CFRの年次予防優先事項調査(PPS)は、その16年の歴史で初めて、「外交政策の専門家にとっての最大の懸念は、米国の国益に対する外国の脅威ではなく、国内の脅威の可能性である」とした。
ここで幾つかの分類を行ったが主要なものは次のとおりである。
『日本の進路』編集部
1月1日、BRICSはサウジアラビア、イランなど5カ国を新メンバーに迎え10カ国となった。他方、米国に支えられたイスラエルのジェノサイド攻撃に対するパレスチナやイエメンなど中東・アラブ人民の闘争は発展する。
新年早々、世界構造が激変したことが印象づけられた。もはや米国を頂点とする「先進」資本主義大国・帝国主義が支配する世界は過去のものである。
東京経済大学教授 早尾 貴紀
イスラエル軍は、パレスチナのガザ地区に対して、無慈悲なジェノサイド(大量虐殺)を仕掛けている。死者1万4500人以上、うち子供が5500人以上という大惨事で、この数はますます増えている。
パレスチナ問題を理解するためには、歴史的経過を押さえなければならないが、直近の状況からさかのぼって述べたい。
ハマース(イスラーム抵抗運動)などによる10月7日の武装蜂起について、パレスチナに理解を示す人でさえ、冒頭に「ハマースによる民間人への攻撃は不当であるが……」と言わないとダメなような雰囲気がある。
この蜂起をスタートラインにすることは、大きな誤りである。
蜂起直前、ガザ地区は何が起こってもおかしくない状況にまで追い込まれていた。直視できないほどの惨状、極限状態にあった。 続きを読む
元駐中国、インド大使 谷野 作太郎

(1)次に、これも現役時代、縁を得たインドのことについて少しお話ししたいと思います。私は1995年から98年まで、駐インド大使の任をいただきました。私も家内もすっかりインドにはまってしまいました。暑い? 確かにそうですが、日本と違って湿度はそれほど高くない。40度を超える暑さの中でも水筒をぶら下げながら、インドの友人たちとゴルフに興じたものです。
東京大学社会科学研究所教授 丸川 知雄

日中の平和と友好が大事と考える人々にとって今年(2023年)の夏はなかなかつらかったと思う。いうまでもなく、福島第一原発の敷地内に溜まった核汚染水を処理した水を海洋に放出する作業が始まったからである。日本政府と東京電力は、汚染水に含まれる放射性物質を極力取り除くものの、トリチウムは濾過しても取り除けないので海水で希釈したうえで放出するのだと説明している。
元駐中国、インド大使 谷野 作太郎

3年余にわたったコロナ禍がようやく峠を越え、世の中はその面では、落ち着きを取り戻しつつある昨今ですが、気がついてみると、その間、わが「地球村」の破壊、劣化は恐ろしい勢いで進んでしまったという情況です。
終わりが見えないウクライナ戦争、政治、社会の分断が進み凋落に歯止めがかからない米国、ますます対決を強める米中関係、内向きで猛々しさを増す中国、そしてわが日本も政治の劣化が進み、国際的競争力も落ちていく一方……かくして、ウツウツたる心情で、残り少なくなった余生を送る日々です。
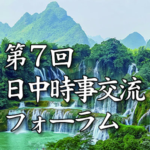
石垣市議会議員 花谷 史郎

日本政府が進める「南西シフト」と言われる自衛隊配備の最前線に立たされている先島諸島にある石垣島より現地の状況をお話しさせていただきます。
2015年11月に石垣島の平得大俣へ陸上自衛隊の配備が発表されてから8年近くがたち、今年3月に駐屯地がとうとう開設されてしまいました。
私は駐屯地が配備された平得大俣地区に畑を持ち、隣接する嵩田地域に生まれ育った当事者として反対運動に参加し、その後市議会議員となり、これまで陸自配備の問題に関わってきています。
石垣島の現状の話の初めに、駐屯地周辺の住民の話をさせてください。
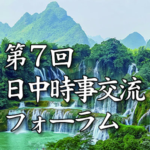
参議院議員(会派「沖縄の風」代表) 伊波 洋一

沖縄では1945年の沖縄戦で県民約9万4千人と、県出身軍人・軍属2万8千人の計12万2千人以上の県民が地上戦で亡くなりました。他都道府県出身兵約6万5千人以上、米軍1万2千人以上、全体で20万人以上が亡くなりました。
その後、米軍統治が27年も続いて、県民の土地が強制接収されて広大な米軍基地が造られ、現在も米軍駐留が続いています。
県民が広大な米軍基地の返還を求め続ける中で、日本政府が県民の反対を押し切って、自衛隊基地建設を強行しており、沖縄の各地で自衛隊基地建設に反対する取り組みが続いています。沖縄県民は、強く戦争に反対しています。
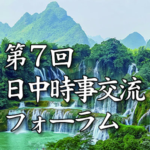
ジャーナリスト 布施 祐仁

ふせ ・ゆうじん
1976年、東京生まれ。フリージャーナリスト。2018年10月、『日報隠蔽―南スーダンで自衛隊は何を見たのか』で石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞。近著に『日米同盟・最後のリスク なぜ米軍のミサイルが日本に配備されるのか』(創元社、2022年5月)、他多数。
「私が幸せそうに見えるとしたら、それは私が幸せだからです。素晴らしい会談でした」
8月18日にワシントン郊外のキャンプデービッド(大統領山荘)で開かれた米日韓首脳会談。会談後の記者会見で、米国のバイデン大統領は満面の笑みを浮かべながらこう切り出した。
米国の呼びかけで行われたこの首脳会談で、バイデン大統領、岸田文雄首相、韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領は「米日同盟と米韓同盟の間の戦略的連携を強化し、米日韓の安全保障協力を新たな高みへと引き上げる」(共同声明)ことで合意した。
『日本の進路』編集部
10月23日、日中平和友好条約発効から45周年を迎える。「国交正常化共同声明での原則」や「平和5原則」などにのっとった両国関係を再確認し、もっと前へ進まなくてはならない。
1931年9月18日に満州事変・中国侵略戦争を本格化させて47年、日本敗戦から33年、ようやくわが国は中国と条約で正常化を実現した。日本は日米安保体制下だったが中国と協力関係を強化する道に進んだ。
琉球大学名誉教授 上里 賢一

沖縄の歴史を振り返って言えることは、東アジア地域の安定があってこそ、平和で豊かな生活ができるということである。
東アジアの中で土地の広さや人口の多さから言って、中国の存在は昔から圧倒的に巨大であり、中国の動向が周辺国の進路に大きな影響を与えることも変わっていない。「唐は差し傘(これほど広い)、大和は馬の蹄、沖縄は針の先」という俚諺には、三者の地理的関係がよく表現されている。ただ、最近の辺野古の新基地建設に対する日本政府の沖縄の民意無視の冷たい姿勢に、「唐は傘のように沖縄を守ってくれたが、大和は蹴散らすだけだ」と揶揄する見方もある。
東アジア共同体研究所長(元外務省情報局長) 孫崎 享

今日日本の外交安全保障政策は米国との「同盟関係(本質は日本の米国への隷属)」を最優先し、この枠内で動く。日中関係は日本や中国独自の選択で動くのではなく、米国の指示の範囲内で動く。
そして、「米国の中国への認識、関与の仕方が変わると、それは日中関係にも影響する」ことを十分に認識しておく必要がある。