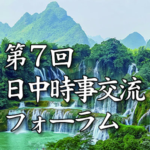
「沖縄を再び戦場とさせないために」
日中・アジアの連携が重要
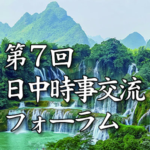
ジャーナリスト 布施 祐仁

ふせ ・ゆうじん
1976年、東京生まれ。フリージャーナリスト。2018年10月、『日報隠蔽―南スーダンで自衛隊は何を見たのか』で石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞。近著に『日米同盟・最後のリスク なぜ米軍のミサイルが日本に配備されるのか』(創元社、2022年5月)、他多数。
「私が幸せそうに見えるとしたら、それは私が幸せだからです。素晴らしい会談でした」
8月18日にワシントン郊外のキャンプデービッド(大統領山荘)で開かれた米日韓首脳会談。会談後の記者会見で、米国のバイデン大統領は満面の笑みを浮かべながらこう切り出した。
米国の呼びかけで行われたこの首脳会談で、バイデン大統領、岸田文雄首相、韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領は「米日同盟と米韓同盟の間の戦略的連携を強化し、米日韓の安全保障協力を新たな高みへと引き上げる」(共同声明)ことで合意した。
沖縄を再び戦場にさせない県民の会共同代表 瑞慶覧 長敏

ずけらん・ちょうびん
東アジア共同体研究所 琉球・沖縄センター長。米州立セントラルワシントン大学、琉球大学卒。元衆議院議員、前南城市長。
「沖縄を再び戦場にさせない県民の会」が今年7月25日に沖縄で発足した。その名の通り、戦争を起こさせないぞという意思で活動する会だ。離島を含む全県的に参加を呼び掛けて、今の時点で(9/18)60を超える個人や団体が呼びかけ人として名を連ねている。最終的には100を超える団体の参加を目指す。大きな数だと言える。

『日本の進路』編集部
10月23日、日中平和友好条約発効から45周年を迎える。「国交正常化共同声明での原則」や「平和5原則」などにのっとった両国関係を再確認し、もっと前へ進まなくてはならない。
1931年9月18日に満州事変・中国侵略戦争を本格化させて47年、日本敗戦から33年、ようやくわが国は中国と条約で正常化を実現した。日本は日米安保体制下だったが中国と協力関係を強化する道に進んだ。
兵庫県宍粟市議会議員 今井 和夫

8月の長崎での全国地方議員交流研修会は延期になりましたが、実はその時に、第1分科会(農業部会)において、次ページの『食料安全保障を推進する自治体議員連盟』設立の提案をさせてもらおうと、第1分科会の世話役の間で話をしていました。
繰り返して私が説明するまでもないと思いますが、鈴木宣弘先生が孤軍奮闘、あちこちで体を壊してでも講演されています。今、日本は食料が危ない。流通が止まれば7000万人が飢え死にする。そんな国は日本だけ。
『日本の進路』編集長 山本 正治
酷暑に豪雨災害、散々な夏が終わり、秋になった。しかし、国民のいのちと暮らしの危機は一段と深刻になりそうだ。
さすがに酷暑は終わるだろう。しかし、台風と豪雨災害は続く。物価高騰も続く。今春の賃上げは「ほぼ30年ぶりとなる水準」(連合)となったが、物価高騰にはとても追いつかない。
琉球大学名誉教授 上里 賢一

沖縄の歴史を振り返って言えることは、東アジア地域の安定があってこそ、平和で豊かな生活ができるということである。
東アジアの中で土地の広さや人口の多さから言って、中国の存在は昔から圧倒的に巨大であり、中国の動向が周辺国の進路に大きな影響を与えることも変わっていない。「唐は差し傘(これほど広い)、大和は馬の蹄、沖縄は針の先」という俚諺には、三者の地理的関係がよく表現されている。ただ、最近の辺野古の新基地建設に対する日本政府の沖縄の民意無視の冷たい姿勢に、「唐は傘のように沖縄を守ってくれたが、大和は蹴散らすだけだ」と揶揄する見方もある。
東アジア共同体研究所長(元外務省情報局長) 孫崎 享

今日日本の外交安全保障政策は米国との「同盟関係(本質は日本の米国への隷属)」を最優先し、この枠内で動く。日中関係は日本や中国独自の選択で動くのではなく、米国の指示の範囲内で動く。
そして、「米国の中国への認識、関与の仕方が変わると、それは日中関係にも影響する」ことを十分に認識しておく必要がある。
参議院議員(会派「沖縄の風」代表) 伊波 洋一

米海兵隊普天間基地のある宜野湾市に住み、離発着する米軍機の爆音に悩まされる毎日ですが、今夏は例年以上にオスプレイやヘリ以外の外来の米軍ジェット戦闘機の離発着回数と爆音が激しいと感じます。沖縄近海で在日米軍の訓練や演習が行われており、米軍機騒音の激化は「台湾有事」に向けた米軍演習の増加と思われます。
東アジア共同体研究所理事長(元内閣総理大臣)

今から45年前の8月12日に日中両国が平和友好条約に署名したことを心からお祝いします。
主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を謳い、すべての紛争を平和的な手段により解決をすることを確認した平和友好条約の意義と有効性は、今日に至るまでいささかも失われておりません。
「沖縄を再び戦場にさせない県民の会」は、麻生発言に対して那覇市で8月13日、「麻生発言に抗議し、発言の撤回を求める緊急集会」を開催した。
山城博治・県民の会事務局長が、麻生副総裁発言は「岸田政権の総意だ」と指摘して、県民挙げての抗議の必要性を訴え開会した。
同会共同代表の瑞慶覧長敏さん(東アジア共同体研究所琉球・沖縄センター長/前南城市長)は、「私たちの国がまずやるべきことは対話・信頼だ」と力を込めた。
ジャーナリスト(元共同通信客員論説委員) 岡田 充

福島第1原子力発電所の溶け落ちた核燃料を冷却する汚染水の海洋放出が近づいている。
日本政府やメディアは、国際原子力機関(IAEA)の「国際的安全基準に合致」とした調査報告書(7月4日)によって、海洋放出の安全性と正当性が保証されたかのように主張する。
だが報告書が「排出の安全性を判断する内容ではない」ことを、どれほどの人が知っているだろう。報告書で「お墨付きを得た」とし、地元・福島の漁民や市民団体、中国や太平洋の島嶼国など海外の反対を「非科学的」「外交カードにしている」などと決めつけるのは、あまりに傲慢な態度ではないか。
『日本の進路』編集部
岸田文雄首相、バイデン大統領、尹(ユン)錫(ソン)悦(ニョル)大統領による日米韓3国首脳会談が、米ワシントン近郊の大統領山荘キャンプデービッドで開かれ、安全保障協力強化で合意したという。日米の個別会談では、極超音速兵器に対処する新型迎撃ミサイルの共同開発も確認した。軍事的な3国同盟関係を事実上確認したといってよい。
衰退著しく内外に困難を抱えるアメリカが日本や韓国の協力を必要としたことは間違いない。時代錯誤の大国化願望の岸田首相は、麻生太郎自民党副総裁に言わせたように「戦う覚悟」を示した。
自主・平和・民主のための広範な国民連合 事務局
麻生太郎自民党副総裁は過日、台湾を訪問し、中国を念頭に「台湾海峡の平和と安定には強い抑止力を機能させる必要がある」、そのために「日本とアメリカ、台湾には『戦う覚悟』」が求められるなどと主張しました。「内閣と打ち合わせの上だ」と同行の自民党政調副会長が断言しています。公明党の北側一雄副代表も発言に理解を示したと報道されています。
驚くべき発言で、中国内政への乱暴な干渉、戦争挑発に他なりません。