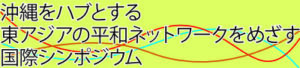若者を先頭に、東アジアで二度と戦争をさせない政治めざして
広範な国民連合 代表世話人 羽場 久美子(青山学院大学名誉教授)

皆さんこんにちは。三つのことについてお話ししたいと思います。
今年は、日清戦争130年、日露戦争120年、昭和100年、敗戦80周年です。二度と大陸と戦争をしない、ということを誓いたいと思います。
国連は創設80周年の記念すべき年です。国連では、原爆投下80周年に核廃絶に向け国際会議なども積極的に取り組まれています。私も4月末、その国際会議に行ってまいりました。 続きを読む