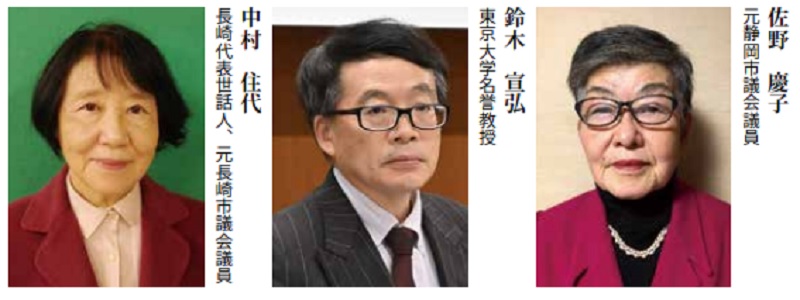政府や社会を動かすのは、
いつの時代も青年の情熱と行動力です
日本青年団協議会会長 杉山 和義

日頃より、自主、平和、民主的な社会づくりをめざし奮闘される皆様の取り組みに、心から敬意を表し、全国の青年団を代表し、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
2025年は、日本にとって極めて重要な一年でした。被爆・戦後80年という節目の年を迎え、私たちは先の戦争の悲劇と平和の尊さを改めて胸に刻みました。しかし、国際情勢は緊迫の度を増し、ウクライナやガザ地区での争いは未だ終わりが見えません。このような不安定な時代だからこそ、核兵器のない平和な世界の実現に向けた運動を、私たちはさらに前進させていかなければなりません。 続きを読む