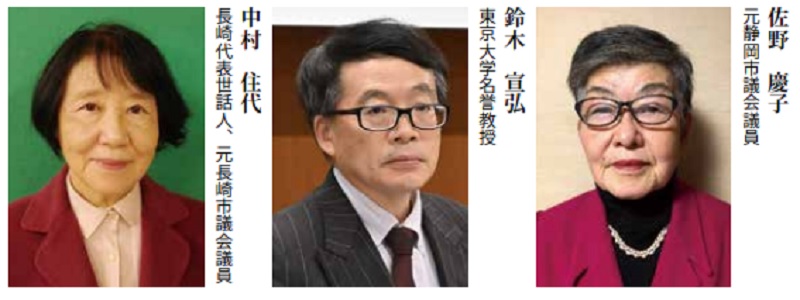再生産可能となる直接支払などの実現に向けて
粘り強く運動展開する
北海道農民連盟委員長 中原 浩一

新年あけましておめでとうございます。令和8年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
さて、昨年の本道農業を振り返りますと、1~3月期は暖冬傾向にありましたが、2月には十勝地方において短期間に120cmを超える記録的大雪を観測し、6~7月にかけての高温・干ばつ、9月には北海道で初めてとなる線状降水帯の発生によって集中豪雨に見舞われるなど、温暖化の影響は各地で農産物の品質・収量の低下のほか、農地の損失等を及ぼしました。 続きを読む