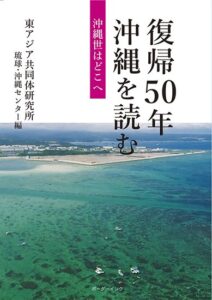米国への従属を転換する覚悟と戦略が問われる
一般財団法人・東アジア共同体研究所理事 高野 孟

今年は沖縄の復帰50年という大きな節目の年で、1972年の沖縄返還協定によって沖縄が27年間の「アメリカ世」を脱して再び「ヤマト世」を迎えてからのこの半世紀を一つの時代としてどう捉えたらいいのか、沖縄の側ではもちろん本土の側も含めて、盛んな議論が沸き起こるものと思われた。そこで、私が属する東アジア共同体研究所の琉球・沖縄センターでは昨秋から準備して、『復帰50年 沖縄を読む/沖縄世はどこへ』と題したブックレットを編んで今春出版した。その第1部では、私が私なりのこの50年の概観的スケッチを描き、それを呼び水にする形で、本文に当たる第2部では、沖縄と本土の50人の多彩な方々に「この50年を考えるためのこの1冊」を選んでその推薦理由を短く鋭く書いてくれるようお願いした。そのような構成にしたのは、この大きなテーマを一つの角度で切り裂くことなど到底できるはずがなく、むしろ逆にさまざまな視点から光を当てて乱反射状態をつくり出すことの方が議論をにぎやかにするのに役立つだろうという判断からであった。
ところが、それから半年が過ぎたが、驚くべきことにわれわれが予想したような復帰50年をめぐる大議論は起きなかった。もちろん現地や本土のメディアはそれなりに特集やシリーズ企画を組んだが、それらはそれだけのこととして流れ去っていき、沖縄の人々が50年を経てもなおどうすることもできないでいる本土による根源的な差別の構造は微動だにせず居座ったままである。
9月には沖縄県知事選があり、辺野古新基地建設に反対する玉城デニーが基地容認の自民党・公明党推薦の候補を破って再選を果たした。この記念すべき年にたまたま巡ってきた選挙で「オール沖縄」陣営に支えられた玉城が勝利したのは重要な政治的な成果ではある。けれども、問題は、県民がいくら選挙や県民投票で明確な意思を示しても、本土政府は一切耳を貸さずに「辺野古移転が唯一の選択肢」と呪文のように言い続け、しかも本土の国民がそのような政府の態度を変えさせようとも思わずに事実上容認してしまっているという、二重であるが故に沖縄に対する根源的な差別構造には、何ら揺るぎがなかったということである。その構造を一夜にして転覆することなどできはしないと分かり切ってはいても、それを揺るがし始めるきっかけくらいはつかめる年にしたいものだと思ったのだが果たせず、虚しく迎えるこの年の暮れである。
復帰は「日米安保条約の下の日本への復帰」だった
なぜこんなことになったのか。一つの有力な着眼点は、大田昌秀元知事の言葉を借りると「沖縄の人々が切実に希求したのは『平和憲法の下への復帰』だったにもかかわらず、逆に『日米安保条約の下への復帰』」になってしまったことではないか。沖縄人の本当の祖国と言えば「アメリカ世」はもちろん、その前の「ヤマト世」66年間をも飛び越えた琉球王国しかあり得ないというのに、そこに目を瞑って敢えてヤマトを〝祖国〟と呼び、それこそ当時のオール沖縄の諸団体を総結集して「沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)」を組織して運動を繰り広げたのは、「平和憲法下の日本への復帰」がかないさえすれば米軍直接占領下の苛烈な軍事支配から逃れられると信じたからである。ところが、復帰してみて分かったのは、復帰した先は「平和憲法下の日本」ではなく「日米安保体制下の日本」だったということである。
これを本土の側から見れば、佐藤栄作首相が登場して早々の1965年8月に現職の首相として戦後初めて沖縄を訪れ「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国にとって戦後は終わらない」という〝名文句〟を吐いてにわかに沖縄の復帰を政治課題として提起してきた時、彼らの側は、①米軍の直接占領下で在沖米軍基地をこれ以上維持するのは住民感情からして難しく、②そのため施政権を日本に返還して住民感情を和らげるとともに、今後は日本政府が責任を持って住民を抑えて米軍に安定的に基地を提供し、またその諸費用も負担することとする、③併せて日本自衛隊が大きく南進し、米軍の補助的役割を沖縄にまで拡張する――つまり「日米安保体制下の日本」に沖縄を組み込もうとするものであることを、はっきりと企図していた。第2次佐藤内閣の総務長官だった床次徳二があからさまに述べたように「沖縄の人たちは日米安保体制の一環として復帰を考えてもらいたい」ということだったのである。
「日米安保条約下の日本復帰」に無自覚な欺瞞
ところがこの当時の本土の国民というか革新運動の側は、1960年の岸信介内閣による日米安保条約の改定に反対する闘争を戦い切れずに挫折し、ということは、「平和憲法下の日本」を優勢にして「日米安保条約下の日本」を抑えつけることに失敗して、池田勇人内閣の「イノチよりカネだろう、おまえら」の高度経済成長路線に半ば搦め捕られてオロオロしている時期だった。その時に沖縄から「平和憲法下の日本」に復帰したいと言われても「どうぞ安心して『平和憲法下の日本』の懐に抱かれてください」と言えるような状況では到底なかった。しかし欺瞞的なことに、「復帰自体はいいことだ」という誰にも反対し得ない抽象的な大前提を据えた上で、それを「県民の復帰運動の成果だ」と、これもまた半分は本当なので否定するのは難しい理由を付けて、大いに歓迎した。復帰先に指名された日本が実は「平和憲法下」ではなくて「日米安保条約下」でしかないことを告白し、そういう日本にしか沖縄を迎えることができない自分たちの運動の非力を土下座して謝るべきだったというのに。私は当時まだ20歳代で、革新陣営の一角で駆け出しの記者として執筆・講演活動に励んでいたが、そのような復帰を祝うかのような革新側の欺瞞性というか没主体的な偽善性に我慢ができずに異論を立ててその陣営から追われる羽目になった。
「平和憲法下」と「日米安保条約下」の対立軸
第2次大戦後の日本の戦後史を、「平和憲法下の日本」と「日米安保条約下の日本」との相克として捉えるのは極めて有力な座標軸の立て方である。が、これは実は、より普遍的なレベルでは「国連憲章下の〔21世紀的〕世界」と「米国覇権下の〔20世紀的〕世界」という現今の世界理解の基本図式の一部と位置付けられる。国際連合は、二度と国際紛争解決の手段として武力を用いないという全人類的な決意表明とともに1945年に発足し、それを受けて翌年成立した日本国憲法は、国際社会がそのような「平和を愛する諸国民の公正と信義」の道に進むに違いないことを「信頼して、われらの安全と生存を確保しようと決意し」(前文)、世界に先駆けて戦争と武力による威嚇・行使は「永久にこれを放棄する」(第9条)ことを宣言した。
ところがこの不戦への崇高な誓いはあまりにも儚く、47年3月のトルーマン米大統領の「全体主義vs自由主義」の対決図式のドクトリンと49年のNATO結成、それへの西ドイツの加盟に対抗した旧ソ連・東欧諸国による55年ワルシャワ条約機構(WTO)設立によって、世界を二分して核を含む武力で脅し合う「冷戦」に突入した。
冷戦が終わるということは、「敵対的軍事同盟」の時代が終わり、国連憲章に代表される「協調的安全保障」の時代がようやく緒に就くことを意味していたので、ソ連のゴルバチョフ大統領は即座にWTOを解消した。
が、米国のブッシュ父大統領は冷戦の終わりをそのように理解せず、「冷戦という名の第3次世界大戦でロシアに勝利した米国は、もはや敵なしの唯一超大国だ」と妄想を膨らませ傲慢の極致に上り詰めた。NATOを解消せず、欧州域内のみならず域外の危機にも共同対応するよう目的を変更(外延化)して存続させたばかりか、旧東欧・ソ連邦諸国を次々に加盟させる「東方拡大」を推進した。それが今日のウクライナ戦争の遠因ともなった。
アジアでも似たことが起きる。日米安保条約は旧ソ連の対日上陸侵攻の危険が消滅した後も北朝鮮の核ミサイル開発や中国の軍拡などに脅威を横滑り(外延化)させて存続させられたばかりか、日本により主体的な軍事的役割を分担させるベく集団的自衛権を解禁させ、オーストラリアやインドまで巻き込んだ4カ国同盟による中国包囲網づくりに追い立てている(日米安保の「西方拡大」)。結局のところ日本人は、50年前も今も、同じように、いやますますだらしなく、「米国覇権下の世界」で「日米安保条約下の日本」として生きることに甘んじていて、だから沖縄に新しい米軍基地が建設されようと、自衛隊のミサイル部隊が増強されようと、何ら痛痒を感じないという以前に関心すら抱くことはないのである。そりゃあそうでしょう、米国大統領が来日するといっても横田米空軍基地に降り立ってそこから都心の大使館近くまで専用ヘリで飛ぶという無礼を働いても、それに抗議することのない従属国の国民が、沖縄の基地についてだけ怒りの声を上げるなどということがあるわけないだろう。こうして、沖縄の復帰50年を見つめれば見つめるほど浮き彫りになるのはむしろ「日米安保条約下の日本」の惨めさなのである。
「イノチかカネか」
沖縄の物差し
さて沖縄の側からこの50年に当てる物差しの一つは「イノチかカネか」ということだろう。復帰協の初代会長で1968年に初の公選主席となった屋良朝苗はまさに沖縄の「イノチの叫び」を代表する政治家だったが、彼が目指した「基地なき沖縄」は夢のまた夢にすぎなかったという現実に苦悩しつつも復帰後も県知事を務めた。それに対し本土政府は新たに「沖縄開発庁」を設置、「沖縄振興開発計画」を打ち出して、基地がなくならずイノチが脅かされ続けている分をカネで慰めようとする作戦に出る。やがて78年には屋良からその後継者である平良幸市へと受け継がれた革新県政の流れを断ち切って、自民党が推す西銘順治知事が誕生して3期12年を務め、本土のカネをうまく使って「開発の時代」をつくり上げた。
それに対する反動として90年11月に登場したのが大田昌秀知事で、彼は県が米国と直接交渉してでも基地を順次返還させるための「基地返還アクションプログラム」とその跡地を活用した「国際都市形成構想」とを掲げて、「基地なき沖縄」を現実のものとする道筋を描いたが、やはり本土政府によって押しつぶされた。その後は、琉球石油の稲嶺惠一、沖縄電力の仲井真弘多と経済界出身の自民党知事による第2の「開発の時代」、「イノチよりカネだ」の政治が16年も続くことになった。
そこに2014年の選挙で躍り出たのが翁長雄志で、彼は今までは「保守は経済、革新は尊厳だったが、これからは殺伐とした豊かさではなく誇りのある豊かさ、潤いのある豊かさだ」と、この50年を彩ってきたイノチとカネの間の行ったり来たりを止揚していくイマジネーションを示しただけで逝ってしまった。その後継者である玉城デニーは2期目を迎えていよいよその遺志を実行しなければならないが、それには県民からの支持だけでは足りない。本土の国民が彼を支え勝利することを通じて、アメリカへの従属を転覆する覚悟とそのための戦略がどうしても必要となる。
沖縄は、日本の情けなさ、醜さを映し出す鏡であることを今一度、確かめ合いたいと思う。
(見出しは編集部)