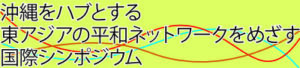即時停戦こそ求められる
本質は米・NATOの代理戦争
伊勢崎 賢治 東京外国語大学教授 に聞く

ウクライナ戦争から1年。昨年の開戦から、僕は即時停戦を言い続けてきました。それが和田春樹先生たちの耳に留まって、それ以来一緒に声明文を国連事務総長宛てに出すなど、いろいろな働きかけをしてきました。日本人は、「停戦」と「終戦」の違いがあまり分かっていないと思います。日本は、かつての戦争で、停戦にならず終戦までいってしまった。もし停戦がされていたら? 3月10日の東京大空襲も、沖縄戦も、広島・長崎も回避できたか? これは歴史のイフですが、本来ならその違いをいちばん分かる国民でなければならないと思うのです。








 長崎市で10月8日、〝新時代の日中平和・友好関係をめざして〟とのスローガンを掲げて「日中国交正常化50周年記念集会」(実行委員会主催)が開かれた。当初、9月19日を予定していたが台風の影響に伴い延期、43団体・法人と100人を超える個人の賛同を得て開催が実現した。県民、市民約150人が参加、来賓に長崎華僑総会、与野党国会議員秘書、県議会日中友好議員連盟の4県議をはじめ佐世保・厦門市青少年交流協会、県貿易協会、労組の代表者らも出席。多数の祝電・メッセージも寄せられ文字通り各界・各層、超党派による県民集会となった。
長崎市で10月8日、〝新時代の日中平和・友好関係をめざして〟とのスローガンを掲げて「日中国交正常化50周年記念集会」(実行委員会主催)が開かれた。当初、9月19日を予定していたが台風の影響に伴い延期、43団体・法人と100人を超える個人の賛同を得て開催が実現した。県民、市民約150人が参加、来賓に長崎華僑総会、与野党国会議員秘書、県議会日中友好議員連盟の4県議をはじめ佐世保・厦門市青少年交流協会、県貿易協会、労組の代表者らも出席。多数の祝電・メッセージも寄せられ文字通り各界・各層、超党派による県民集会となった。