自治体が生み出す貧困問題と自治体議員の役割
北海学園大学経済学部教授 川村 雅則
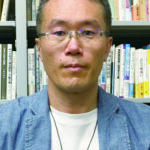
失業率は低いが
貧困率が高い日本
日本は、諸外国と比べて、失業率が低いのに貧困率が高い国である。働いていながらにして貧困という問題が広くみられる。理由の一つであり貧困の給源地となっているのが非正規雇用という領域である。非正規雇用は今や4割弱を占めるに至っているが、この問題は女性に大きく偏って発生している。雇用の非正規化は、「夫は仕事、妻は家庭」といった固定的な性別役割分業をはらんで進んできた。非正規雇用・貧困問題の解決にあたっては、ジェンダーをめぐる問題の解消を念頭におく必要がある。ILOによって提唱されるディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)においても、そのことは課題として強く意識されている。
まともな暮らしを保障しない日本の最低賃金制度
労働者がフルタイムに働きまともな暮らしをしていく上で、どのくらいのお金を必要とするのか。この疑問に答えるのが最低生計費に関する調査だ。生活実態調査・持ち物調査や価格調査などに基づき、中澤秀一氏(静岡県立大学短期大学部准教授)が各地の労働組合と手間暇をかけて調べたところ、単身で、時給1500円は必要だと試算されている。物価高騰下で行った最新の調査では1700~1900円は必要だと試算された。もちろん、賃金に依存して生活する度合いが高い日本では、これだけでは不十分だ。教育費や住まいの費用まで射程に入れ、社会保障・公的支出を拡充する必要がある。
いずれにせよ、今の最低賃金は低過ぎる。日本の最低賃金はOECD加盟国の中で低い部類に入る。かつては生活保護と最低賃金に逆転現象が生じていた。近年、最低賃金は従来に比べると大きく引き上げられているとはいえ、今年度の全国加重平均額(予定)は1121円にとどまる。石破政権は、2020年代に最低賃金1500円の実現を掲げたが、物価高騰を踏まえると、早急に、さらなる引き上げが必要である。そのための強力な中小企業対策も並行して進めることが必要である。
市町村で4割を占める
非正規公務員
以上のような問題を前に、自治体議員にはどんなことができるだろうか。自治体は、地域で最大の雇用主であり、かつ、さまざまな仕事を民間事業者に発注する存在(発注者)でもある。自治体は、地域の雇用に深く関わっている。これらの雇用をまともにする取り組みが議員に期待されている。
現状は、自治体が貧困を生み出してしまっている。例えば、非正規公務員問題。20年度から導入された会計年度任用職員制度の下で働く職員は、全国でおよそ100万人に及び、市町村では4割を占める。そのおよそ4分の3は女性である。
任用の適正化が掲げられながらも、不安定な雇用(有期雇用の乱用)が制度化され、しかも、実効性ある雇い止め規制がないために、民間ではあり得ない雇い止めが生じている。賃金面では、「給料表」上、低い箇所に位置付けられ、経験を積んでも賃金はまったく上がらないか、上がってもすぐに打ち止めとなる。経験の蓄積・スキルの向上が適切に評価されていないのである。不安定雇用と低賃金という、非正規雇用の二大問題に彼(女)らは直面している。それにもかかわらず、公務員であるがゆえに彼らの労働基本権は制約されていることも強調したい。
男女共同参画、女性活躍のための条件整備は足下から
もっとも、こうした賃金の特徴について首長や行政はこう「説明」する。彼らは扶養されているのだから、専門性を要しない簡単な仕事に就いているのだから、と。無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)がそこにないだろうか。議員にお願いをしたい。自治体の男女共同参画基本計画や特定事業主行動計画(女性活躍推進法)の策定・推進にあたっては、上記のような問題を意識してほしい。女性管理職の少なさなど「ガラスの天井」には言及されていても、女性の非正規雇用・低賃金など「ベタつく床」への言及はみられない。
自治体が貧困を生み出しているのだから、市民社会や民間部門への啓発に先だって、まずは「自己点検」「自己分析」の姿勢が必要ではないだろうか。
労働条件ダンピングを
生み出す入札等制度と、それを防ぐ公契約条例
自治体の仕事は、直接雇用の公務員だけでは回らない。建設工事のほか、委託や指定管理など、多くの民間事業者・労働者の力が必要とされている。その際、事業者を選定するには入札/公募制度を介することが一般的である。そこでは、事業経営・技術の継承や、労働条件の維持・労働力の確保を困難にするような激しい価格競争が展開されてきた。重層下請構造の建設工事でも、委託や指定管理の分野でも、低賃金の労働者(下請け労働者・一人親方・非正規雇用者)が活用され、彼らの賃金は最低賃金にへばりつくほどである。そして委託等では、入札等で事業者が代わるたびに労働条件がリセットされる──このような状況が続いてきた。結果、これらの仕事は恒常的業務であるにもかかわらず、労働契約法第18条の無期転換権が事実上剝奪されることになっている点にも留意されたい。
以上のような諸問題の防止を期待されているのが、自治体と民間との間の公契約を適正化する条例、すなわち、公契約条例である。予定価格の積算の際に設定された労働者への支払い賃金水準を守らせることで、労働条件ダンピングによる苛烈な受注競争を防ぐことができる(雇用継承の条項も設ければ、入札等を介しても労働者は安心して働き続けることができることも強調したい)。結果、まともな価格での仕事の発注が可能となり、事業者が適正な利益を得て、労働条件も適正化され、もって、地域経済の好循環を生み出すことが期待される。その影響は大きい。
自らのマチの現状把握を
自治体が生み出す「貧困」やそれへの対策を駆け足で見てきた。
地方創生の一環で、会計年度任用職員制度の「改善」が政策課題として浮上してきた。関係者の運動の成果でもある。ただ一方で、「公共サービスの産業化」で直営事業の民間化が狙われており、楽観はできない。そのような中で、二元代表制の一翼を担うはずの自治体議員は、自らのマチの現状把握ができているだろうか。
公務・公共の仕事に従事する者は、市民の暮らしや命を守るエッセンシャルワーカーである。その彼らが生活困窮に陥っている現状が看過されてはいないか。行政が保有する情報を広く共有し、政策立案に生かしていこう。それこそが「自治基本条例」や「議会基本条例」が目指す姿である。
参考文献・資料
•川村雅則「公契約条例制定の全国的な推進に向けて」『社会主義』第736号(23年10月号)
•川村雅則「⾮正規公務員が安⼼して働き続けられる職場・仕事の実現に向けて」『KOKKO』第55号(24年5月号)
•川村雅則編著『お隣の非正規公務員──地域を変える、北海道から変える』北海道新聞社、25年
