中国の最優先課題は世界一流の社会主義強国、中華民族の偉大な復興
平和と地域安定追求こそわれわれの選択
共同通信客員論説委員 岡田 充

米ロの代理戦争としてのウクライナ戦争
今日のメインテーマは台湾有事ですが。ここ1週間のウクライナの動きを見ると、全体として米ロのある意味では代理戦争的なところがあるわけです。米ロお互いの挑発がかなり刺激的になったなという気がしています。
共同通信客員論説委員 岡田 充

今日のメインテーマは台湾有事ですが。ここ1週間のウクライナの動きを見ると、全体として米ロのある意味では代理戦争的なところがあるわけです。米ロお互いの挑発がかなり刺激的になったなという気がしています。
衆議院議員(元自民党幹事長) 石破 茂

議員になってもう37年目です。右からは左と言われ、左からは右と言われる。実に不思議な立ち位置にありますが、絶対的な立ち位置は変わっていない。言っていることは変わっていないんです。
平成の時代はおそらく、三つのものが本質的に変わった、そういう時代だったと考えます。一つは間違いなく「戦後」が終わったということだと思います。昭和20年に少年兵として従軍された方も今は90歳になられる。田中角栄先生は従軍された経験がおありでしたが、ご存命中に、「あの戦争に行ったやつがこの日本の中心にいる間は大丈夫だ」とおっしゃっておられた。「だけど、そういうやつがいなくなった時が困るんだ、だからよく勉強してもらわなければいかんのだ」ということをよく言っておられた。その戦後が終わった。
国際地政学研究所理事長(元内閣官房副長官補) 柳澤 協二

まず、ウクライナ戦争に触れておきたい。プーチンの狙いについて、世界が間違えていました。まさか、ウクライナに攻め入ることはないと思っていた。ところが戦争を始めてしまった。
背景には、ソ連崩壊後のNATOの東方拡大を巡って、西欧・アメリカとロシアの間の信頼醸成がなされてこなかったことがあると思います。だからと言ってプーチンの行為を免責するわけにはいかない。これは国連憲章に違反する、第二次世界大戦後の世界秩序を覆す暴挙です。

広範な国民連合は衆議院議員会館で3月14日、シンポジウム「台湾有事を避けるために――日本の安全保障を考える」を開催した。冒頭、柳澤協二さん(元内閣官房副長官補、安全保障・危機管理担当)が「台湾有事を避ける」基調的な提起を行った。続いて、石破茂さん(衆議院議員、元自民党幹事長)が日本の安全保障政策について問題意識を述べ、岡田充さん(共同通信客員論説委員)と羽場久美子さん(青山学院大学名誉教授)がコメントした。会場から、「台湾有事」ともなれば最前線となる沖縄から伊波洋一参議院議員と新垣邦男衆議院議員が、また、実際に戦闘を担うことになる自衛隊OBとして林吉永さん(空将補)が、それぞれ問題意識を述べた。
日本のロシア・東欧史研究者を中心に歴史家たちは3月15日、「ウクライナ戦争を1日でも早く止めるために日本政府は何をなすべきか」と題した訴えを出し、日本政府などへの働きかけを強めている。「ロシア軍とウクライナ軍は即時停戦し、停戦交渉」を始めるため、「日本、中国、インド三国の政府にウクライナ戦争の公正な仲裁者となるように要請」している。この訴えを支持し、「なしうるあらゆる努力を」呼びかける。(編集部)
世界国際学会(ISA)アジア太平洋会長/
グローバル国際関係研究所所長/
神奈川大学教授・青山学院大学名誉教授
羽場 久美子

本稿は、第2回「日中時事交流フォーラム」(2月27日)での問題提起に筆者が加筆修正されたもの。見出しとも文責編集部。
ウクライナはヨーロッパとロシアのはざまにある「非常に大きな小国」です。不思議な言い方ですけれども、ドイツとポーランドを合わせたくらいの、ドイツの2倍の領土があります。ウクライナはすでに主権と領土保全の領有権を持つ国です。現在、ウクライナの首都までロシアの軍隊が迫っており、そうした中で多数の犠牲が出ていることはたいへん遺憾だと思います。
第2回「日中時事交流フォーラム」が2月27日、オンラインで開催された。当フォーラムの日本側代表を務めている羽場久美子・青山学院大学名誉教授が、「EU・NATOの間で引き裂かれるウクライナ―境界線でせめぎあう大国―」をテーマに報告し、華語シンクタンクの彭光謙理事長がコメントを述べた。中国側からは徐長銀・同シンクタンク執行理事長、龔剣・同シンクタンク事務局長が、日本側からは、第1回報告者であった丸川知雄東京大学教授をはじめ三十数人が参加した。凌星光教授が仲介役を務め、杜世鑫氏が通訳を担当した。
今回の交流は、ロシアの軍事侵攻でウクライナ市民の犠牲が相次ぎ、他方、経済制裁などロシアへの圧力が強まる情勢下で行われた。羽場教授の、日中が連携して東アジアから平和的解決に動くべきとの提起を受けて、真剣な意見交換がなされたことは大いに意義深い。以下概略。
福岡県日中友好協会事務局長・広範な国民連合全国世話人 中村 元氣

今年で「日中国交正常化50周年」になることを記念し、お祝いする「九州日中友好大会」が1月25日に福岡市の中国駐福岡総領事館で開催された。
この大会は、九州6県(福岡・佐賀・大分・熊本・宮崎・鹿児島)の日中友好協会と同総領事館の共催で開催した。
当日は、新型コロナウイルス感染拡大も考慮して、メイン会場を同総領事館にして、各県の日中友好協会や(公社)日中友好協会と、中国の北京・南京の友好協会などをオンラインで結んで行った。大会には、メイン会場の約20人(人数制限した)の他に、九州各県や中国からの参加者も含めて全体で約100人が参加して盛大に行われた。
大石あきこ 衆議院議員に聞く

木元 茂夫

あまり注目されなかったのだが、昨年2月3日に「日英外務・防衛閣僚会合」が開かれた。その共同声明に次のようにある。
「4大臣は、海洋安全保障における日英協力が引き続き優先事項であるとの前向きな進捗を再確認し、これを更に強化していくこと及び地域の安全保障を維持するためにリーダーシップを発揮していくことにコミットした。4大臣は、空母打撃群の東アジア訪問が日英防衛協力を新たな段階に引き上げる機会となるよう、協力していくことを確認した。4大臣はまた、この訪問が自由で開かれたインド太平洋に資するとの認識を共有した」
共同通信客員論説委員 岡田 充

まるで坂を転げ落ちるように「戦争シナリオ」が完成しようとしている。日米両政府は「台湾有事」が近いとして、昨年4月の首脳会談では日米安保の性格を「地域の安定装置」から「対中同盟」に変更。さらに台湾有事に対応するため、米海兵隊が自衛隊とともに南西諸島を「機動基地」にし、中国艦船の航行を阻止する「共同作戦計画」の推進にゴーサインを出した。それからわずか一年足らず。野党の反対や議論もないまま、安保法制が発動されようとしているのはどうしたことか。憲法に抵触する恐れがある戦争シナリオが独り歩きする現状は、戦争に近づく危険に満ちている。 続きを読む
『日本の進路』編集長 山本 正治
1月7日、日米安全保障協議委員会(日米「2+2」)が開催され、「(日米は対中国の)戦略を完全に整合させ」「南西諸島を含めた地域における自衛隊の態勢強化の取り組みを含め、日米の施設の共同使用を増加させる」と確認した。対中戦争準備と疑われて当然だ。沖縄は、「再び戦場化」の危険にさらされる。岸田首相は1月17日、国会の施政方針演説でこうした方向を確認した。
日本が、中国「抑止」で「有事」をつくりだしてはならない。敵基地攻撃能力獲得など論外だ。
参議院議員(会派『沖縄の風』代表) 伊波 洋一

今年は、日本と中国の国交正常化から50年であり、沖縄の施政権が米国から日本に返還された50年目の年でもある。しかし、年明け早々の1月7日に開かれた日米の外務・防衛担当閣僚による「日米安全保障協議委員会(日米2+2)」で、日米両政府は、南西諸島で台湾有事を想定した対中国戦争の準備作業に入ることを確認したと言える。
丹羽宇一郎 氏に 聞く
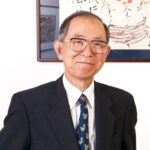
にわ・ういちろう 1939年、愛知県生まれ。現在、伊藤忠商事株式会社名誉理事、公益社団法人日中友好協会会長。2010年、民間出身では初の中華人民共和国特命全権大使に就任。著書多数、近著に『会社がなくなる!』(講談社現代新書)。
日本と中国が50年間、武器をとらないで、戦いをしないで平和に過ごしてきたのはまさに記念すべきことです。口でのいざこざはありましたが、武器をとって戦いをやったことがないというのは日本と中国というだけでなく、世界全体を見ても、歴史上記録に残るようなことだと思うんです。そういう意味で今年はまさに50周年記念と同時に、平和というのはこういうことなんだと、歴史に残るような平和な姿を世界に示しました。武器をとってのいざこざがないのは、日本と中国以外にないだろうと、誇りに思ってこの50周年記念を祝うべきだと思います。国民連合の皆さんがたも努力されてきたということに、大変に感慨深い思いを私はもっております。日中両国とも皆さんもぜひこれは誇りに思っていいと思うんです。