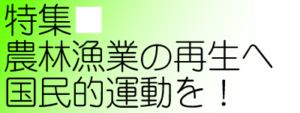
全日本農民組合副会長 鎌谷一也(前鳥取県畜産農業協同組合長)
はじめに
当てにならない政治経済情勢の中で、生活と営農、暮らしをどう守っていくか。真剣に考えなければならない時代。
政治をつくり上げるものも国民、住民だが、その民がまず自分たちで、地域や自分たちを守るためには何をすべきか、主体的に考えなければならない。最近、「独立国を創ろう」「自分たちの小さな国家創りを」と言っているが、そのぐらいの気概での取り組みが必要だ。そうした取り組みによってこそ、地域の主体性の確立と独自性の確保、力強い地域間の連携、都市を包囲する地方・地域からの反撃と包囲網、そして農村と都市の連携・連帯が生まれるような運動の基軸が展望できるのではないかと思う。
さらに、グローバリズムに対抗するには、地域の取り組みだけでなく、国際的な民の連帯・団結も必然的に問われてくる。いわゆる万国に連なる国際主義である。先日実施した田植え体験交流に、大学の研究生として来日しているアメリカ人家族、ベトナム人、エジプト人が参加していたが、エジプト人いわく「ナイル川流域で行っている田植えは、まったく日本の田植えと一緒です」。水田の畔から、世界はつながるものだと、考えさせられた。
世界をよくし、連帯と団結を深めるためにも、地域から、自ら暮らす領域での個別的な取り組みを実践し、その取り組みを通じて普遍的な課題を共有化、共同の取り組みとして展開していくことも大切である。
地域での活動家(とりわけ地方議員等)が住民・農民の先頭に立って実践し、運動の広がりを望むものである(本稿では、別に寄稿した協同組合への想いと少々の実践例を紹介した文章を少し手直ししたものである)。
農村の再生、コミュニティへの取り組みとして、現場で取り組んできたいくつか実践を紹介したい。

一つは、鳥取県畜産農協と京都生協・鳥取県生協等生協グループとの産直活動での協同間協同の取り組みである。鳥取の産直活動は、牛乳が1970年から約50年、産直牛肉が約40年の歴史をもつが、この産直の歴史は省略し、21世紀での取り組みに焦点を当てて紹介したい。二つ目は、2008年に始めた広域農業生産法人の組織化である。これは小さな農協づくりとして、地域の農業の再生として取り組んでいる。三つ目は、同じく同エリアで取り組んでいる共生の里づくりである。地域の団体による活性化だけでなく、連携組織として生協を含めた地域活性化の取り組みであり、食と農の再生の一つの手段として取り組んでいる。最後は、酪農民だけでなく、農協、生協、地域の企業を含めて出資し、10年20年後の畜産や食料確保に備えるという「みんなの牧場」の取り組みである。
1、鳥取県畜産農協と京都生協等生協グループとの産直の取り組み
①グローバリズムに抗する産直、地産地消の取り組み
グローバリズムとの出会いは、1999年シアトルのWTO交渉であった。農民として、シアトルでのWTOの交渉に接する機会があり、衝撃を受けたのはグローバリズムに対するアメリカ市民の反対のエネルギーであった。高校生から、有機農業者、組織労働者等、シアトルでの5万人集会では、それぞれ参加者・団体が主体性をもち、反対の声を上げ、その力強さに驚いたものである。
99年の闘いの流れが20年を経て現在のアメリカの動きにつながっていることを考えると、根は深いし、歴史を感じる。この訪米の時に、翻って日本の状況を考えたのだが、グローバリズムに対する日本の農民運動、労働組合運動、協同組合運動は、どれをとっても、あまりにも静かなのが日本の現状であった。そうした中で、われわれにできるのは、グローバルな視点を持ちつつ、ローカルに具体的に活動を展開することであり、産直活動や地産地消への取り組みであった。
②センチュリープラン~百年続く農畜産業を目指す~
2001年から10年の取り組み
01年、「百年続く農畜産業を目指そう」と、京都生協と鳥取県畜産農協は、産直の取り組みとして新しい牛づくり「こだわり鳥取牛(乳オスの肥育)」をスタートさせた。
取り組みの中身は、健康、エコロジー「循環」、国産、安全、低価格という5つのコンセプトのもと、牛の餌に飼料稲・飼料米や食品副産物を利用する。堆肥を水田に還元しながら、水田の活用と安全な自給飼料を作る。環境保全や循環型農畜産業への取り組み、さらには自給率向上など、生産者と消費者双方が考えながら協力して取り組む。また「サシ」から赤身の肉へ、「健康に育った牛の健康なお肉をいただく」という食肉に対する消費者の価値観をもっていただくなど、食への価値観を一緒に創っていく、無駄に飼養せず若齢肥育とする、というものであった。
伸びたWCS、拡大する飼養頭数、深まった産直交流
取り組みの結果はどうであったか。飼料稲を食べた産直牛肉を提供していく。そして、その裏づけがあるからこそ、鳥取県東部での飼料稲の作付けは01年20ヘクタールから40、80ヘクタールと倍々ゲームで伸ばすことができた。さらに、資源循環として堆肥を水田に還元することを前提としたので、堆肥処理の課題が解決され肉用牛の増頭が可能となった。現在では、その取り組みが発展し、東部地域全域で190ヘクタールのWCS(稲発酵粗飼料=ホールクロップサイレージ、稲の実と茎葉を同時に収穫し発酵させた牛の飼料)、飼料米の作付けも144ヘクタールとなっている。また、農協の直営部門として、飼養頭数も毎年200頭平均で拡大ができ、総飼養頭数は00年200頭規模から、最高では08年に2400頭まで拡大することができた。生産と消費がつながることにより、大胆な水田利用の拡大や牛の増頭が可能だったと言える。
新しい牛づくりを通じて、単に産地交流だけでなく、毎月の京都生協の店頭での試食販売や交流など、出かけて行っての交流機会も増加、さらに年2回の鳥取フェアや毎年の産直フォーラムの開催など、産直交流の在り方も深まったと言える。
真に産直提携が問われたBSE
01年9月11日アメリカのテロの前日に発生したBSE(牛海綿状脳症)。発生後、一時的には、京都生協の供給高も前年対比で6割も減少したが、2頭目が発生した11月30日には、前年を上回る供給高まで回復した。当時、いつ流されてもおかしくない濁流の中、押し流されないよう生産者は足を踏ん張っていると訴え、2カ月間で約100人の生産者・職員が京都に出向いた。生産者の訴えを受け止め、体を張って牛肉の販売をしていただいた生協職員、当時の理事長には、「生協は生産者の砦になりうる」とまで言っていただいた。本当に苦しい時に真価を発揮するのが産直と言っていた父の声を実感できた時であった。
食の安全、食品の偽装問題等が急速に問題視される契機となったのもBSEである。BSEの発生前から、こだわり鳥取牛の取り組みの中で、トレーサビリティーを唱えていたが、生協との産直の優位性は、こうした消費者ニーズに直結できるという点にもあった。1999年の牛乳のハセップ(HACCP=60年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された食品の衛生管理の方式)対応や、精肉工場のハセップ仕様の建設、さらに2005年には業界では初めてと思うが、生産現場である牧場から、製造加工施設、直場所等の店舗、営業に至るまでのISO22000(食のマネジメントシステム)を取得することができた。これも、産直の中での相互の情報とニーズへの対応ができたことによる。また、大学生協との提携の中で、学生の酪農家へのインターシップ制度による交流体験もこの当時の取り組みであった。
さらに、07~08年当時の低乳価、生産調整、飼料価格の高騰といったトリプル苦の中で、暗闇の海を漂流しているかのような先の見えない不安感に襲われつつも、乗り越えることができたのも、生協との産直であった。食べ物を通じて連携する生協と、農協の歴史を振り返れば、数多くの財産が形成されてきたと言える。
③総合農協と連携した畜産基盤の強化と直売所での地産地消の拡大
生協との産直による出口を確保する一方で、産直の中での取り組みは、地域に、いろいろな事業展開をもたらしている。県内の総合農協との連携により、空き牛舎を借り受けて増頭し生産基盤を強化する一方、総合農協の直売所にテナント出店もさせていただき、地域の支持を得て牛肉販売を拡大してきた。地産地消の展開である。もう一つは、飼料稲の刈り取りや資源循環を一手に引受けるコントラクター組織の組織化である。02年よりスタートさせ、飼料稲営農集団と畜産農家集団の連携など、県東部一円の耕畜連携のセンター機能的な役割を果たしてきた。
水田での飼料生産から牛肉生産、処理加工、販売という一連の流れが螺旋的に太くなる。産直と地産地消で、地域からの拡大型地域循環経済システムの可能性が見えてきた時期であった。
2、地域からの農と食の再生(未来づくり)への取り組み
①深まる課題と2010年代の取り組み
「2001年からの取り組み」を通じて、課題も明らかとなった。
 一つは、耕作放棄地の拡大や高齢化など、地域農業・農村の将来に対する危機感である。そして、BSEをきっかけとして強まった消費者の権利(消費者基本法の改正)の強まりのなかで、もはや食と農は、生産者というよりもむしろ消費者の主体的な課題であり、消費者が関わっていくことこそ重要という認識であった。08年から12年の産直フォーラムでは、農と食の再生をテーマに、生産者だけでなく、産直で、また消費者が地域に関わることにより、地域の再生をどう図るかをテーマにしてきた。産直で始まり、産直で育てる―「環境保全型・循環型農畜産業と循環型社会」を目指すとしたものである。(つづく)
一つは、耕作放棄地の拡大や高齢化など、地域農業・農村の将来に対する危機感である。そして、BSEをきっかけとして強まった消費者の権利(消費者基本法の改正)の強まりのなかで、もはや食と農は、生産者というよりもむしろ消費者の主体的な課題であり、消費者が関わっていくことこそ重要という認識であった。08年から12年の産直フォーラムでは、農と食の再生をテーマに、生産者だけでなく、産直で、また消費者が地域に関わることにより、地域の再生をどう図るかをテーマにしてきた。産直で始まり、産直で育てる―「環境保全型・循環型農畜産業と循環型社会」を目指すとしたものである。(つづく)
